子供の健康を願う!妊娠から1歳の誕生日まで家庭・神社の儀式集
 妊娠、出産、そして赤ちゃん育児には、喜びや楽しさが満ちています。でも、不安もつきものですよね。
妊娠、出産、そして赤ちゃん育児には、喜びや楽しさが満ちています。でも、不安もつきものですよね。
日本には、妊娠・出産そして育児にまつわる人生儀礼がたくさんあります。節目をお祝いすることで、こうした不安をスッキリ洗い流しましょう。
日本には人生の節目に行う儀式が沢山あります
私たちが住む日本では、人生の節目にさまざまな儀式を行う風習があります。妊娠から1歳のお誕生日までの短い期間には特に、人生儀礼がたくさんあります。
「人生儀礼」ってなに?それは節目の年齢で行われる儀式です
人生儀礼とは、七五三や成人式といった人生の節目にあたる年齢で行う儀式のことです。私たちの人生には、さまざまな節目があります。
人生儀礼は仏教や神道の儀礼と結びついていたり、儒教の考え方にのっとったものなどがあります。
むかしは医学も科学も発達していなかったため、小さな子どもが無事成長して成人するまでにはさまざまな危険がともないました。
また、家族だけでなく、一族や地域社会みんなで子どもを守り、育てていました。社会の一員として受け入れてもらうための、「お披露目」という意味も兼ねています。
そのため、妊娠から1歳のお誕生日を迎えるまでの短期間に、さまざまな人生儀礼があるのでしょう。
また最近では、ハーフバースデーのような儀式も行われるようになってきました。地域性の高い儀式もいろいろあります。
逆に沖縄や北海道のように、あまり人生儀礼をおこなわない地域もあります。家庭によって重んじる点は違ってくるので、家族で話しあって決めると良いですね。
神社やお寺を参詣するとき
儀礼のなかには、神社やお寺を参詣して行うものもあります。その際は、いろいろ守らなければいけないマナーがありますね。
安産祈願や初宮参りなどで神社仏閣をお参りする際は、パパとママもラフすぎる服装はひかえましょう。安産祈願の場合、ママはマタニティウエアで大丈夫です。
祈祷を受ける場合は祈祷料が必要になります。祈祷料は紅白蝶結びの水引をかけたのし袋に入れ、神社なら「玉串料」「初穂料」、お寺なら「祈祷料」「祈願料」と表書きします。
神社では二礼二拍手一拝が基本です。お寺では合掌が基本で、柏手は打ちません。お寺に行く際は、もしお持ちならお数珠・お念珠を持参すると良いですね。
妊娠中の儀式「安産祈願」でお産の無事を祈りましょう

安産祈願は、妊娠中に行う儀式です。まだ生まれていなくても、命が宿った時から「親子」となります。その気持ちと自覚を育む儀式といえるでしょう。
安産祈願
安産祈願は、何事もなく妊娠期間を過ごし、無事安産で赤ちゃんを産むことを神仏に祈る儀式です。神社でもお寺でも受け付けています。
五ヶ月目に入ると安定期になり、流産の確率もぐっと減ってママの体調も落ち着きます。そこでこのころに腹帯を巻きはじめると良いとされているのです。
戌の日は十干十二支の「戌」、12日に一度やってくる日です。戌は「犬」に通じ、イヌはお産が軽いため、それにあやかり安産を願うようになったと言われています。
実は、世界でも妊娠中の女性が腹帯を巻く風習があるのは日本だけとされています。医学的根拠は解明されていませんが、保温や保護といった意味もあります。
昔ながらの腹帯は岩田帯といわれるさらしの布です。扱いが難しいため、最近ではコルセットやガードルタイプのものや、骨盤を支えるトコちゃんベルトなどもあります。
安産祈願では、着帯の儀にそなえて腹帯をお祓いしてもらいます。安産祈願は戌の日と考えているママも多いのですが、戌の日以外でも多くの神社仏閣では祈祷を受け付けています。
東京の水天宮などでは、戌の日は非常に混みあい長蛇の列となります。体調と相談し、都合の良い日に安産祈願を受けるとよいでしょう。
気になる場合は、事前に安産祈願でお祓いしてもらった腹帯を、戌の日に巻きはじめると良いですね。
水天宮をはじめ、大分県の宇佐神宮や宮城県の鹽竈神社、神奈川県の大巧寺(おんめさま)など、安産祈願で有名な神社仏閣は全国にあります。
また全国には子易神社や子安観音といった名前をもつ神社仏閣が点在しています。こうした社寺も、安産祈願にご利益があるとされ、人気がありますよ。
安産祈願で気をつけること
安産祈願で有名な神社やお寺は全国にあります。場所によっては戌の日だけ祈祷を受け付ける所もあるので、事前に電話で確認しておきましょう。
祈祷料は5千円から1万円ほどが相場です。また神社ではお米や清酒、お寺なら生花やお供物を持参するところもあります。
安産祈願といえば腹帯です。腹帯を持参すればお祓いをしてくれるところが多いので、持参すると良いですね。
腹帯は、新品のものやさらしの岩田帯に限るという神社もありますし、使用済みのものでも構わないという神社もあります。
新品の腹帯を持参する際は、包装から出して風呂敷などに包み、社務所の受付でお渡しするとよいでしょう。
2人目、3人目の出産の場合は、使用済みの腹帯を持ち込むこともあります。使用済みの腹帯でもOKという神社なら、洗濯して清潔なものを風呂敷に包んで持参しましょう。
神社やお寺によっては、祈祷済みの腹帯やコルセットを販売しているところもあります。また祈祷の授与品のなかに岩田帯が入っていることも多いですね。
なかには京都のわら天神こと敷地神社のように、独特の風習がある神社もあります。事前に公式サイトや電話で確認すると安心です。
安産祈願はパパとママ、そして両家の両親も一緒にお参りにいくことも多いものです。
お腹にいる赤ちゃんの親として、赤ちゃんのために最初にできる心づくしのひとつです。
赤ちゃんへの最初の、そして最大のプレゼント「命名~名前をつける」
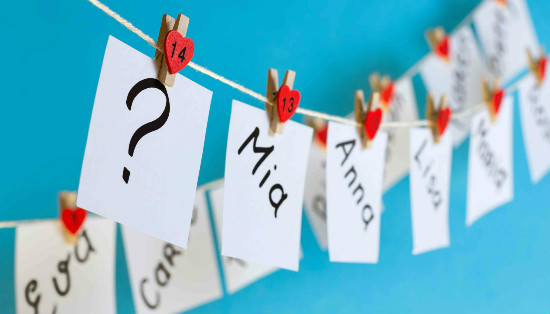
赤ちゃんの名前を決めることを「命名」といいます。赤ちゃんにどんな名前をつけるか、多くのパパママが悩むのではないでしょうか。
命名の方法
最近では産婦人科で使用する機器が発達しているため、出産前に男女が判っていることが多いですよね。
そこで出産前に名前を決めておく家庭も多いようです。書店には、たくさんの命名に関する書籍が置いてあります。
近年、人名に使用できる文字が格段に増えました。また、最近では「キラキラネーム」と呼ばれる、ちょっと読みにくい漢字を使用した名前も増えているようです。
子どもは大人になり、老人になるまで一生その名前を名乗り続けなければなりません。そのことを考慮し、いつまでも子どもが誇りに思ってくれるような名前を慎重に考えましょう。
命名をする際には、下記のような方法があります。
- 親が考える
- 両家の両親などの親族が考えたり、家で継がれている文字を使う
- 神社やお寺などに依頼する
実は私自身、お寺で名前をいただきました。父が好きな漢字をひとつえらび、その字を入れた名前をいただいたそうです。
多くの神社仏閣では命名を受け付けています。姓名判断に基づく命名をと考えている場合などは、利用してみてもよいのかもしれません。
命名の決まりごと
命名は、出生届までに決める必要があります。出生届は出産の日から14日以内に役所に提出しなければなりません。出生届は24時間受け付けてもらえます。
名前が決まったら、命名書と呼ばれる紙に名前を墨書し、神棚や床の間などに飾る家庭もあります。
命名書は、出産した産院や神社などで頂けることもありますし、赤ちゃん用品ショップでも販売しているところが多いですね。
父方の祖父などに書いていただくのが一般的ですが、決まりはありません。また一度飾った命名書は、お宮参りなど節目に取り外し、手形足形などと一緒に仕舞っておきましょう。
赤ちゃんの誕生をお祝いする「お七夜」お披露目もかねています!

その昔、日本でも赤ちゃんの死亡率が高かった時代は、産まれてから数日間を乗り越えることが節目とされていました。
誕生後最初のお祝い
お七夜は、赤ちゃんが生まれてから7日目に行うお祝いです。赤ちゃんの誕生を祝い、親族にお披露目をする意味があります。
昔は出産から数日間を乗り越えられない赤ちゃんも多く、無事7日間を乗り越えたことを節目としてお祝いしたようです。
もともとは内孫になる父方の祖父が、家に生まれた子を披露するために開催していました。しかし、現代では家族の在り様も大きく変化しています。
遠方に里帰り出産するママも多いですよね。また7日目というと、ママは退院したばかりで体調はまったく戻っていません。
赤ちゃんも新生児期ですし、低体重児などの場合は退院していないこともあります。そこで、最近ではお七夜を盛大に祝う家庭は少なくなってきました。
ママがお祝いを切り盛りをしなければならない場合は、ママの体調との相談になります。ママの体調がすぐれない場合は、この時期はしっかり休んで、授乳と新生児のお世話に専念しましょう。お祝いはまた別日にしてあげればよいと思います。
我が家では、赤ちゃんとママの退院祝いをかねて、ささやかなお祝い膳を家族で囲みました。双子出産の時は、残念ながら双子とも入院中で家にはいませんでした。
お七夜と命名書
命名で決まった名前は、命名書に記してお七夜に披露するのが一般的です。ささやかなお祝いで済ませる、もしくはお七夜はしない家庭でも、そのポイントを押さえておくと良いですね。
氏神様への赤ちゃん誕生の報告「お宮参り」
お宮参りは、出産の無事を感謝し、赤ちゃんの成長を願って行う神社・お寺への参詣です。最近は、だいぶ様変わりしてきました。
お宮参り今昔
お宮参りとは、氏神様に赤ちゃんが誕生したことを報告し、無事に成長することを願うための儀式です。初宮参りともいいます。
昔は、赤ちゃんが誕生してから男の子なら31日目、女の子なら33日目に参詣すると良いとされていました。
しかしお宮参りの風習には地域差が大きく、さらに時代に合わせてしきたりも変わってきています。
産後1ヶ月は、ママも産後の疲れや育児疲れが出るころで、夜中の授乳で寝不足も強い時期ですよね。赤ちゃんも1ヶ月健診が終わったばかりで、まだ首が据わっていません。
そこで、最近では3ヶ月位をめどに行う家庭も増えています。赤ちゃんとママの体調や機構などを考慮し、良い時期を選べばよいでしょう。
さらに地元の氏神様だけでなく、いろいろな神社仏閣が選ばれています。基本は氏神様への報告ですが、新興住宅地やマンション住まいだと氏神様がわからないこともありますね。
お宮参りの作法
お宮参りは、両家の両親が立ち会うことも多いですね。参詣する場合、古来父方の祖母が赤ちゃんを抱き、産着と呼ばれる着物を上からかけるのが正式です。
産着は初着と呼ばれたり、祝い着・掛け着と呼ばれることもあります。男の子なら熨斗目(のしめ)模様、女の子は友禅柄が一般的です。
しかし父方の祖母が必ずしも抱っこしなければならないわけではありません。家庭の事情によって、母方の祖母やママ、パパが抱っこしても大丈夫です。
また、お寺でお宮参りをすることも可能です。お寺の場合は、「初寺詣で」などと呼ぶこともあります。
安産祈願でお世話になった先へ「お礼参り」に行きましょう
お礼参りは、安産祈願でお世話になった神社やお寺に、無事安産できたことを報告し、感謝するための儀式です。
お礼参りとお宮参り
お礼参りは、安産祈願のお礼のために神社仏閣を参詣することを言います。安産祈願と同じ社寺にお宮参りに行く場合は、かねていると考えてもよいでしょう。
ただし、安産祈願とお宮参りが別の社寺になる家庭も少なくありません。我が家では、安産祈願を東京の水天宮で受け、お宮参りは父方の地元の神社にお参りしました。
こういった場合は、やはり安産祈願でお世話になった神社仏閣にお礼参りに行った方が良いでしょう。神社やお寺の中には、安産の報告があるまで毎朝祈祷を行うところもあります。
お礼参りに行くときは、安産祈願でいただいたお守りやお札を持参します。納札所がある場合はそちらに納め、ない場合は受付で申し出ましょう。
神社やお寺によっては、小石などを持ち帰ってお守りにしたり、安産枕などを預かってお守りにするところもあります。
お礼参りの際にお返しください、とされているところが多いので、お礼参りに訪れる時は忘れずに持参しましょう。
安産枕などの場合は、新しいものを作って二つに増やし、奉納するなどのしきたりが決まっていることもあります。
我が家でも、お宮参りとは別に、パパとふたりで水天宮へお礼参りにうかがいました。お礼参りの作法も、神社仏閣によっては明記されているので参考にしてくださいね。
お礼参りの時期
お礼参りの時期は、いつと決まっているわけではありません。ママの体調が整ってから参詣するか、パパや祖父母に代参してもらってもよいでしょう。
前述したように、安産の報告があるまで祈祷が続けられるところもあります。そういった社寺の場合は、なるべく早めに電話でも構いませんので安産の報告を入れると良いですね。
赤ちゃんが一生食べ物に困らないために!「お食い初め」を祝いましょう

お食い初めは、赤ちゃんが今後食べるものに困らない人生を送れるようにとの願いをこめて行う儀式です。
食べ物への願い
私たちの命を作っているのは食べ物です。そこで、赤ちゃんが一生食べるものに困らないように願いをこめて、日本では「お食い初め」という儀式を行ってきました。
あまり日にちにこだわらない家庭も多いですね。お宮参りを生後3ヶ月くらいで行う場合、お食い初めも一緒に祝う家庭もあります。
お食い初めは、専用の塗り膳に、祝い料理を盛り付けて行うのが正式です。祝い料理は尾かしらつきの鯛やお赤飯などが並びます。
生後3ヶ月ほどの赤ちゃんは、まだ離乳食も始まっていません。実際にはお祝い料理を赤ちゃんが食べることはありません。
ただお箸で料理をつまみ、赤ちゃんの口許へ運んで食べさせるフリをします。さらに「歯固めの石」と呼ばれる小石を口にくわえさせる儀式も行います。
お食い初めあれこれ
自宅でお食い初め膳を用意するのはちょっと大変です。そこで料亭や仕出し屋さんでお願いすることもおすすめです。初宮参りの後、家族で会食しつつ祝うと良いですね。
昔ながらの祝い膳ではなくても、離乳食用の食器にささやかなご馳走を用意し、家庭で祝うという方法もあります。
そのため、初宮参りでは授与品として離乳食用の食器やカトラリーを贈られることも多いですね。歯固めの石を授与品にしている神社もあります。
古来、お食い初め用の塗り膳一式は、母方の祖父母から贈られるのが一般的でした。そこで、最近は離乳食用の食器を贈ってもらうこともあるようです。
離乳食用の食器にこだわりのあるママも少なくありません。「陶器のものを」「名前を入れてもらいたい」といった要望がある場合は、伝えておくと良いでしょう。
無事100日過ごせたお祝い「百日参り」
赤ちゃんが生まれてから100日ほど経過した頃に、「百日参り」という儀式を行う地方もあります。
百日参りとお宮参り
百日参りとは、赤ちゃんが無事100日を過ごしたことを感謝し、今後の成長を祈るための儀式です。「ももかまいり」と読みます。
お宮参りと大変似ていますよね。お宮参りは生後30日前後、百日参りは生後100日前後で区別する地域もあるようです。
ただし百日参りをお宮参りに替えるところも多いので、両方とも必ず済ませなければならない、ということではありません。
もちろんどちらも行う家庭もあります。パパとママの実家で風習が違い、お宮参りと百日参りどちらを重視するか意見が異なる場合もあるでしょう。
そういった場合は、まずパパとママで意見を合わせ、それから両家の両親に穏やかに意向を伝えます。
「しきたり」をなにより重視する家庭もあれば、「金銭面」を重視する家庭もあります。自分の実家がどちらかを理解し、冷静に話し合えば、妥協点も見つかるかもしれません。
一番に考慮するべきなのは赤ちゃんとママの体調です。そこを重視しつつ、両家の意向をすりあわせて、都合のよい時期に神社・お寺を参詣するとよいでしょう。
出産祝いを頂いた!できるだけ早く「内祝い」を返しましょう

赤ちゃんが生まれると、出産祝いをいただきます。出産祝いをいただいたらお返しをしなければなりません。それが「出産内祝い」です。
出産祝いを頂いたら
赤ちゃんを出産したら、周囲の方から出産祝いをいただきます。近しい人ではパパとママの両親から、友人や職場の同僚など、さまざまな方からいただきますよね。
出産祝いは、お産後すぐにいただくものです。出産入院中に赤ちゃんとママをお見舞いに来て、その時持参する人も多いですよね。
日本ではお祝いの品をいただいたら、それに対して「お返し」をするという風習があります。出産祝いのお返しのことを「出産内祝い」と言います。
内祝いは、できるだけ早めにお返しするのが基本のマナーです。出産祝いを産後1ヶ月以内に頂いた場合は、産後1ヶ月が過ぎた頃にお返しをしましょう
産後1ヶ月を過ぎてお祝いを頂いたら、その都度やはり1ヶ月以内にお返ししていきます。贈答に関するマナーは地域差も大きいのですが、金銭がからむだけにシビアな問題です。
内祝いの贈り方
内祝いは、頂いたものの金額の半額程度のものをお返しするとよいとされています。現在はネットでだいたいの値段を調べることができるので、チェックしておくと良いでしょう。
値段がよくわからないものでも、頂いたものの金額の3分の1以下の値段になってしまうと失礼にあたる場合もあります。また頂いたものより高額なものをお返しすることも失礼です。
1万円のものをいただいたら5千円前後、5千円のものをいただいたら2~3千円のものがよいでしょう。
しかし産後1ヶ月は、ママも体調が戻っていませんし、赤ちゃんもまだ新生児期です。赤ちゃんを連れてデパートめぐりをするのは大変ですよね。
そこで、最近ではネットで内祝いをセレクトできるサービスを利用するママが増えています。赤すぐなど、老舗デパートと提携しているところもありますよ。
のしも内のし・外のしが選べるようになっていますし、メッセージカードもつけられます。赤ちゃんの写真やプロフィールも入れられますよ。
ネットで内祝いを選んで、遠方の方ならそのまま発送してもらえます。手間もなく、産前の余裕があるうちにある程度目星をつけておける点も嬉しいですよね。
近場の方でお祝いを持参してくださった方には、やはりお返しを持参してご挨拶に行く方がよい場合もあります。
そういった時には、自宅にまとめて内祝いを届けてもらい、あらためて持参するという方法もあります。
地域によっては、お赤飯やおまんじゅうを持参することもあります。ママは里帰り中でも、パパの実家や自宅の方でお赤飯・おまんじゅうを配るケースもありますね。
こうしたしきたりや風習についても、事前にパパを通じて両家の両親にたずねておくとよいでしょう。
人気のアイテム
では、最近どんなアイテムが人気を呼んでいるのでしょうか。出産祝いの贈り主によって、選ぶアイテムも変わってきます。
両親へのお礼なら、赤ちゃんの名前入りのお酒などは喜ばれますよ。逆にあまり親しくない方に名前入りアイテムを贈ると、ご迷惑になることもあるので注意しましょう。
赤ちゃんの出生体重と同じ重さのお米ギフトも人気があります。名前が入っているものでも、消費できるものなら大丈夫でしょう。
あまり賞味期限のないお菓子などは、高齢者の家庭や独身の方、夫婦だけの家庭には不向きです。
普段あまり交流がなく、好みも生活スタイルもわからない方に贈る場合は、カタログギフトという方法もあります。意外と喜ばれるものですよね。
職場一同、友人一同から頂くこともあります。そういった場合は、タオルやバスボムセットなどちょっとしたものを、ひとりひとりにお返しするという方法もありますよ。
6ヶ月目を祝う「ハーフバースデー」パパママも頑張りをねぎらいましょう

ハーフバースデーとは、欧米で行われてきた習慣で、生後半年を祝うものです。最近日本でも流行しています。
半年間お疲れ様!
ハーフバースデーは、生後6ヶ月目のお誕生日を祝う会です。最近ハーフバースデーを祝う家庭も増えてきました。
生後半年は、ママもパパも赤ちゃんがいる生活や育児に慣れて、赤ちゃんも寝返りなど大きな成長を見せてくれるころです。
離乳食を可愛くアレンジしたり、お部屋を飾り付けて写真を撮るなど、家庭で楽しくお祝いする方が多いようですね。素敵な写真が残せるように、いろいろ工夫してみましょう。
生まれてはじめての節句をお祝いしましょう!「初節句」のあれこれ
女の子は桃の節句、男の子は端午の節句をお祝いする風習は、今でも各地でさかんに行われています。
初節句とは
初節句とは、男の子なら端午の節句、女の子なら桃の節句を初めてお祝いすることです。それぞれ5月5日、3月3日に祝います。
いつどんなお祝いをすればよいのか、双方の実家とあらかじめ相談しておくと良いですね。住んでいる地方が違う場合は、特に早めに問い合わせておくと安心です。
生まれた月が初節句に近く、すぐにお節句がやってくる場合は、お祝いを翌年に延ばしても大丈夫ですよ。
節句人形を買おう
初節句でポイントになるのは、節句人形です。桃の節句ならひな人形、端午の節句なら武者人形を贈り、飾る風習があります。
節句人形は専門店のほか、デパートでも販売しています。専門店なら年中販売していますが、特設販売ならひな人形はお正月すぎ、武者人形は桃の節句すぎからスタートします。
ひな人形は、昔は7段飾り、8段飾りが当たり前でしたが、現在ではコンパクトに飾って収納できるものも増えています。
武者人形は逆に、着られるものも人気があります。昔ながらの武者人形は鎌倉様式でしたが、最近は実在の戦国武将バージョンが人気ですね。
マンションなど飾る場所も収納場所もない、という場合は、ひな人形ならお内裏様とお雛様だけ、というセットもよいでしょう。武者人形も、かぶとだけのセットもあります。
節句人形は、母方の祖父母から贈られるというしきたりの土地が多いようです。しかし、最近では夫婦が好みやスペースに応じたものを選ぶことも増えています。
赤ちゃんが生まれたら、双方の両親に相談し、しきたりを重視するか、予算やスペースを重視するか方針を決めるとよいでしょう。
初節句の祝い方
初節句の祝い方は、地方によって大きく異なります。お正月飾り同様、節句人形は直前に飾ることは良くないという地方が多いようですね。
地域によってはこいのぼりや鍾馗ののぼり旗、掛け軸などを飾る場合もあります。屋外に飾るものは、4月をすぎて天気の良い日から外に出すとよいでしょう。
お節句の当日は、桃の節句ならちらし寿司やひなあられ、はまぐりのお吸い物といったご馳走で祝うのが一般的です。ひし餅型のケーキも最近は人気がありますね。
端午の節句では、地域によってちまきの場所と柏餅が主流の場所があります。かぶとやこいのぼりをかたどったケーキも販売されます。
昔は、初節句でお祝いをいただくことも多く、お祝いを頂戴した方を招いて宴席を設け、ご馳走をふるまう風習がありました。
しかし、最近は大々的に祝う家庭は少なくなりました。とはいえ、お赤飯や紅白まんじゅうを配る地域も残っています。
こうした派手なお祝いをしなくても、パパママだけ、もしくは両家の祖父母を招いてささやかにパーティーを開いてはいかがでしょう。思い出に残りますよね。
桃の節句は桃の花を、端午の節句はしょうぶの花をそれぞれ飾るとよいでしょう。また、端午の節句ではしょうぶの葉を入れたしょうぶ湯に入る地域もあります。
私の出身地では、しょうぶの葉を頭に巻くと賢い子に育つと言われていました。こうした写真を残しておくことも記念になりますね。
節句が終わったら
初節句が終わったら、翌年に向けて節句人形やこいのぼり・のぼり旗などを片付けなければなりません。
たいていの場合は収納の仕方が節句人形の説明書に記されています。また、梱包から出す時に、箱に何が入っていたか書いておくと良いでしょう。
人形は大変デリケートなものです。必ず手袋やマスクをして、丁寧に扱いましょう。傷みが来にくくなります。
ひな人形は、早めに片付けなさいと言われます。あまり長期間出しておくと傷む原因にもなるからです。また、端午の節句の鯉のぼりもその後天気がぐずつくことがあるためです。
どちらも節句が終わったら、できるだけ早めに片付けましょう。天気の良い、乾燥した日に片付けるとよいでしょう。
その他にも地域によって色々なお祝い、行事があります
その他にも、地域によっていろいろな行事を行うことがあります。地元で行われている行事なら、参加してみると良い記念になりますよ。
元気に育つ願いをこめて
では、実際にどんな行事があるのでしょうか。
- 初山祈願
- 子預け・預け子祈願
- 赤ちゃん相撲
このようなものが地域性のあるお祝い、行事となります。
初山祈願とは、1歳前の赤ちゃんが夏前に神社へ参詣することをいいます。浅間神社では、初山参りで赤ちゃんのおでこに朱印を捺します。
子預け・預け子祈願とは、幼子を一時神様や仏様に預けて、子ども時代を無事乗り切るための行事です。昔は「捨」という字を子の名前につけることもありました。
赤ちゃん相撲・泣き相撲は、赤ちゃんを抱いた力士が土俵でにらめっこをさせ、元気な泣き方を競うという行事です。全国各地の神社で行われていますよ。
初めての誕生日!思い出に残る演出をしてあげましょう

パパとママにとって、はじめてのお誕生日は感慨深いものがありますよね。小さかったわが子も、ハイハイやあんよが上手になり、言葉が出始める子もいます。
一升餅の風習
古くから、日本各地で「一升餅」という風習が受け継がれています。1歳のお誕生日に、一升、つまり1.8リットル分のお米をついて作ったお餅を担がせるという風習です。
1升分のお餅の重量は約1.8キロ。大人でもかなり重いもので、やっと立てるようになった赤ちゃんは担げないこともあります。
風呂敷に包んで背負わせたり、リュックに入れて担がせたりと、いろいろな方法があります。また必ずしも立てなくても大丈夫ですよ。
最近では赤ちゃんの名前をお餅に入れたり、後で食べやすいよう小分けになっているものもあります。
初誕生日を祝おう
1歳のお誕生日ころには、離乳食も後期に入り、食べられるものも増えています。ハーフバースデーよりもよりご馳走らしいメニューでお祝いしてあげましょう。
また、フォトスタジオで記念写真を撮る家庭も多いですね。生まれた日から、毎月同じ日に写真を撮り重ねていくと、成長がはっきりわかって良い記念になりますよ。
儀式は愛情の証!それぞれが素敵な日になりますように
1歳のお誕生日までに行う儀式は、赤ちゃんへの愛情の証しでもあります。できるだけ記録に残し、物心ついてからどれだけ愛されて育ったのかを伝えてあげてくださいね。
各儀式には地域性、両家の考え方の違いなど色々と考慮に入れなければならない点があったり、お祝いの参加者の体調によってという面もあるので、都度周りと相談をしつつ、赤ちゃんにとって素敵なお祝いの日としてあげられるように心がけてくださいね。
MARCH(マーチ)では、妊娠や子育ての先輩たちが、ためになる情報を毎日配信しています!新米ママ&パパはぜひご覧ください♪

まだデータがありません。










