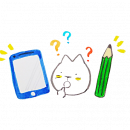小学生の持ち物収納アイデア!ランドセル・教科書が散らからず快適

ただいま~!と子供が帰ってきて、ランドセルがその辺に転がっている……。
明日の道具をそろえた後に、教科書がぐちゃぐちゃになっている……。
小学生あるあるかもしれません。しかし、見ている親の側としてはとてもストレスですよね。
このままじゃいけない!散らかっているのが嫌だ!と思ったら、すぐに収納方法を改善してみましょう。
散らかるストレスをなくし、探す手間を省くためのアイデアを、どうぞ参考にしてみてくださいね。
この記事の目次
小学生の持ち物を収納するときのコツ!収納するときのきまりを考えよう
物が散らかりやすい原因を考えると、実はしまう場所に決まりがないから、ということがあります。
子供が自分でしまう場所のルールを作るのはとても難しいので、まずは親が収納のためのきまりを作ることが大前提となります。
その決まりについては、大きく分けて3つ作ることが大切です。
- ものを置く場所の決定
- ラベリングでものの住所を示す
- 適正量を保つ
こうすることで、出す時もすぐ探せて、戻す時もすぐに戻せます。
置き場所の決定
考えられる場所としては、リビング、子供部屋、玄関とあります。リビングや子供部屋は分かるとして、なぜ玄関なのか?
それは、登校前と帰宅時に必ず通る場所だからです。必ず通る場所に置き場所を作るのは、ものをしまうのに余計な回り道をしなくていいということです。
リビングも、子供が帰ってきて必ず通る場所であるのなら、とても有効な置き場所になります。
特に、リビングで宿題をする機会が多いという場合は、ランドセルや教科書類置き場としても第一候補になります。
あまり子供が出入りしない子供部屋なら、学期末に持ち帰ってくるものだけを置く場所として活用することをお勧めします。
ランドセル・教科書を置く場所のアイデア
小学生の学用品のメインともいえるのが、ランドセルと教科書。
この大物を置く場所をすっきりとさせることで、大部分が片付くといっても過言ではありません。
基本的にはこの2つはセットでしまうと考えたほうが良いです。
【ランドセル】上に置く?下に置く?
ランドセルの置き場所を決めたら、もう一つ、どの高さに置くかを子供と話して決めましょう。一般的に人は目線の高さくらいの場所が一番物を置きやすいとされています。
それでは、ランドセルは胸の高さに置くのが一番ベストなのか?
それはズバリ、「子供による」です。
何しろランドセルは重い!この事実を忘れてはいけません。
また、子供の性格上、上に持ち上げるのすら面倒……という場合もあったりします。
そういった場合におすすめしたい置き場所は、「床置き」。
直接置くのはもちろん良くないので、かごを置いてその中にランドセルを入れさせても良いでしょう。
胸くらいの高さに持ってくるのが問題ない子供は、ランドセルラックやカラーボックスなどの棚に収納させましょう。
ランドセル置き場を決めたら、そのすぐ近くに教科書置き場を作ります。道具をそろえる時に場所が遠いと、手間がかかることでやる気が失われてしまうからです。
その理屈を考えると、ランドセルと教科書入れが一緒になったランドセルラックは、理にかなったものであるといえます。
カラーボックスを利用する際は、ランドセルラックと同じような使い方をするのが良いでしょう。
いずれにしても、子供が置きやすいほうをそれぞれ試してみることが、「決まった場所に戻す」のを長続きさせる秘訣です。
【教科書】取り出しやすい置き方
教科書を出し入れするときに、一番ネックになるのが、「教科書が雪崩を起こすこと」です。
取り出す際にいちいち崩れたりすると、適当に入れ直してごちゃごちゃになる原因になります。
こういった雪崩を起こさないための工夫が2つあります。
- ファイルボックスに小分けして入れる
- ブックエンドできっちり立てる
おすすめはファイルボックスを使った収納です。
ブックエンドはある程度重い本でないと、自立が難しい場合もあるので、教科書が増えてから利用するのがいいかもしれません。
ファイルボックスを教科ごとに分けて使うのもいいでしょう。
基本は1種類につき1スペースにすると管理しやすいので、「国語」「算数」など、科目別にラベルを作ってみてください。
しばらくすると、ものがあふれてきてしまう……適正量を保つにはどうする?
基本的に、ものが多すぎると管理は難しいです。そのため、子供が自分で判断できる範囲の量だけを手元に置きましょう。
これを「適正量」といいます。
チェックする点をしては以下のような感じです。
- 鉛筆や消しゴム、ノートの予備を買いすぎていないか?:予備は1つあれば十分。
- ハンカチやティッシュを持ちすぎていないか?:平日5日分あれば間に合う。
- プリントやノートは終わったものは処分しているか?:必ず1か月に1回は見直す。
とりあえずの置き場を作って対応すれば迷子なし
置き場所も決めたし、ラベリングもした!けれど、どうにも置き場所を決めきれない、置き場所が迷子のものをどうするか。
その場合、とりあえず置き場というカゴを設置するという考えがあります。
こうしたものを「とりあえず」置いておくのに有効です。
とりあえず置き場はあまり容量があるものだと、まだいっぱいになっていないから手をつけなくていいや!という気持ちになってしまいがち。
そのため、とりあえず置き場にとして少し小さめの箱を用意し、あふれる前に対応するようにしてみましょう。
コツを掴んだら、「出したら元に戻す」を習慣づけよう!
ものを置く場所の決定、ラベリングをする、適正量を保つといったコツの他に、もう一つ大切なことがあります。
それは、「出したら元に戻す」を体に覚えさせることです。
習慣づくまでは、見守りやチェックなど親御さんの忍耐力が必要になりますが、ものを元に戻すことが習慣になれば、自然と散らからなくなります。
当たり前のことのようですが、なかなか難しいことでもあります。大人になるまでに、ゆっくりでもいいので身につけたい習慣ですね。
片付けにお悩みの親御さんは、お子さんと一緒にぜひチャレンジしてみてくださいね!
MARCH(マーチ)では、妊娠や子育ての先輩たちが、ためになる情報を毎日配信しています!新米ママ&パパはぜひご覧ください♪

まだデータがありません。