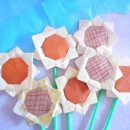同居での子育てで疲れた…ストレスをなくしうつにならないための行動6つ

祖父母世代と同居での子育て。「家事育児を分担してもらえる」「子どもを皆で見守ることができる」など、ママにとっても三世代同居ならではのメリットを感じられる場面はたしかにあります。
しかし、それは嫁姑間がかなりうまくいっている場合や、適度な距離を保てる環境である場合においてです。
実際に多くの場合は、嫌味を言われたり思うような子育てが実現しなかったり、何かと気を遣いストレスが溜まってしまうのではないでしょうか。
この記事の目次
1.子供と一緒に好きな場所に出かけてみよう!
育児において、育児自体が大変と感じたり疲れが取れない場合には、“産後うつ”や“育児ノイローゼ”に陥るのを予防するためにも、ママが一人で出かけてリフレッシュをすることは大切です。
- 「子供を放って一人で出かけて…」と嫌味を言われる可能性
- 気に食わない祖父母に子供を預けて、用もないのに外出していることへの自己嫌悪
もちろん、きちんと祖父母に断わって子供の安全を考えた上でママがリフレッシュに出かけるのは悪いことではありません。しかし、このようなつらさに巻き込まれては本末転倒です。
同居での子育てにおいて、パパが仕事で日中不在の時間はとても長く感じてしまいますよね。
子供に無理のない範囲で、ママの好きな場所に子供を連れて出かけてみてはいかがでしょうか。
- カフェ
- 図書館
- ショッピング(ウインドウショッピング)
- 公園・子育て支援センター等、ママや子供が集まる場
少しの時間でも、外の空気に触れ・好きなものを感じ・外部の人と話すこと等で、「常に祖父母の言動が気になる」というストレスからは解放されることでしょう!
2.パパの協力を得、一人の時間も満喫しよう!
上のように、パパが不在の日にはなかなか子供を預けてのリフレッシュは難しいかもしれません。
しかし、パパがお休みの日には、ぜひ“ママの一人の時間づくり”にも協力を求めてみてください!
月1回でも、数時間でも、美容院に行くだけでも「今はパパに我が子を任せているんだ」と祖父母に気を遣わずに自分の時間をもつことも大切です。
しかし、パパにとっても子供は自分の子供ですよね。「まったく自分で見ようとしない」・「たまにでもママが外出するのに激しく抗議する」といった場合には、同居問題以前の問題です。
パパの意識を高めてもらうため、専門家や第三者を交えての話し合いが必要となる場合もあります。
3.自分で自分を褒めよう!人一倍がんばっているのは変わらない事実!
同居でストレスや疲れがたまってしまう場合には、祖父母の言動がママ自身にとってネガティブなことを言われているように感じる(実際に言われている場合も)のも大きな原因ですよね。
しかし、少し考え方を変えてみましょう。
同居と育児を両立し、その場で「嫁」・「ママ」として振る舞っているだけでもすごいのです!例え祖父母から嫌味を言われても、自分で自分を褒めてあげてください!
- 「もっとがんばろう!」よりも「よくがんばった!」
- 「今日も掃除できなかった」よりも「今日はゴミ捨てに行った、えらい!」
「こんなことして自分を良く思おうと思ってもなぁ…」と落ち込んでしまいそうな方もいるかもしれません。気が滅入っているとなおさらです。
しかし、これはただ「気の持ちよう」や「自分を高めるため」だけの嘘でしょうか?
「同居や子育てをがんばっている」というのも事実、「(完璧な掃除はできていなくとも)ゴミ捨てに行って家をきれいにした」というのも事実です。
4.「割り切り」と「聞き流し」を心がけて!「皆のようにできていない」という悩みは不要
人は多くの場合、他者と比べたり他者に言われたことに対して、ネガティブなこと(自分が負けている、嫌なことを言われた)は記憶に残ってしまいやすいですよね。
嫌なことを忘れるのは難しいですが、気持ちを切り替えることは大切です。
具体的に例を紹介します。
「特別なもの」は「一番良い状態のもの」!自分は自分で良いと割り切って
子育てをしていると家で過ごす時間が長く、自分で発信しなくともSNSや他のママたちが投稿した文や写真を見る機会が多くなるでしょう。
きれいな部屋、凝った離乳食、可愛い手作りベビー服。これらを見て、「育児が大変なのは同じなのに他の方はこんなにがんばっている」と感じる方も多いでしょう。
特に、同居のことで悩んでいる際に「ばあばのお誕生会」等祖父母孝行をしているような投稿を見ると、「自分はママとしても嫁としてもダメだなぁ…」と落ち込んでしまうかもしれません。
来客のために片付けた直後に撮影をしたり、行事等で可愛いご飯を作った際にだけ写真を撮っているケースがほとんどでしょう。また、写真を撮るために子どもそっちのけでSNSに没頭してしまっているママもいるのです。
SNS等を見て「自分はダメだ」と思うのではなく、次のように捉えてみると、ふっと心が軽くなる場合もありますよ!
- 可愛い料理を見たら「クリスマスには我が家でも作ってあげよう」
- 可愛く飾られた部屋を見たら「写真を撮るためにがんばったんだな…」
- 「私は写真映えするような生活はしていないけれど、その分自然体で子どもと関わっている、それが一番子どもにとって良い!」
このように割り切ることで、「あれもこれももっとがんばらないと」と背負い込みすぎずにゆったり過ごせます。
祖父母の「昔はこうだった」・「私はこうがんばってきた」という話が気になる場合もありますね。先人の意見を尊重・参考にするのはたしかに大切なことです。
しかしこれもSNS例に同じく、「がんばってきたことだけを強く言っている」と気楽に捉えておくと良いでしょう。
口では謝り適度に聞き流す!すべてを真に受ける必要は無い!
また同居をしていると、「また○○できていないわね」・「子供ずっと泣いているじゃない」等、祖父母の何気ない一言でも激しく「自分はダメだ」と落ち込んでしまうこともありますよね。
できていないことがあるのは、ママにとってそれは優先順位が低かった(祖父母の思う順番と違った)り、その間子どものために別のことをしていたりしたためです。
また、子供は泣くものですし、うるさく感じたのであれば祖父母があやせば良いのです。毎回泣いたらすぐに抱き上げたり、ママだけがすべてを行う必要は無いのです。
かといって、反論すると問題が大きくなるのも面倒ですよね。(わかってくれる祖父母であれば、そもそも嫌味を言わないですよね。)
そんな時には、口先では「すみません」と言いつつも、適度に聞き流しておけば良いのです。
時には反省することももちろん必要ではありますが、それは本当にママ自身が悪かった時だけでOKです。
祖父母がお小言を言うのが癖になっていたり言いたいだけの場合には、こちらが大人の対応をしておく方が得策です。
5.悩みや愚痴を吐きだそう!家庭外にも頼れる場所はある!
これまで紹介したように、身近な人(旦那さん等)にお願いをしたり、プラスの言葉を出してみる等の気持ちを切り替え術を実践することは、もちろんおすすめの方法です。
しかし、時には自分の本当の感情に向き合ってあげることも大切です。悩みを溜めず、吐き出すことも、精神疾患の予防に効果があります。
同居問題はデリケートな問題です。下手に家で愚痴ってしまっては、旦那さんを刺激して「俺の親をバカにして…!」といった夫婦間トラブル等になってしまう可能性もあります。
旦那さんに気持ちを伝えることは大切ですが、第三者に話をする方が気持ちもスッキリする場合があります。
友人は話しやすい相手!相手の気持ちも考えることで良い気分転換に
友人は気楽に話せて良い相手ですが、愚痴を吐きだしたい際には注意点もあります。
ネガティブな話題が多すぎると友人が疲れてしまったり距離を置かれてしまう場合もあります。
- 同じ内容でもポップに話す(例:「お義母さんが逐一うるさくて~」)
- 要点をまとめて端的に話す
- 聞いてくれることを目的とし、共感や同情を求めない(親友でも他者には他者の考え方があり、必ず一致するとは限りません)
- 聞いてもらったり共感は得られた場合には、必ず「聞いてくれてありがとう」と伝える
- シビアな話を相談したい場合には、予め「相談があるのだけれど」と確認をしておくことで、相手もその気で来てくれる
- 愚痴を吐きだした後には、そのことは忘れて友人との時間を思いっきり楽しむ
直接会うのが難しい場合には、電話やメール・SNSでもOKです。
もちろん、話を聞いてもらおうと連絡を取ってみても、友人とコンタクトがあるとそれ以上に子どもや趣味等別の話題で盛り上がりたくなる場合もあるでしょう。
そんな時には、家庭の問題はオフにして、思いっきりリフレッシュを楽しむのも良いですね!
相談できる専門機関の活用も視野に入れて
話せる相手が思いつかずに行き詰ってしまったり、「このままでは自分がまいってしまう」と危機感を感じるような状況の際には、専門機関を頼ってみるのも一つです。
相談は無料であったり、必要であれば医療機関やより特化した専門家を紹介してくれる場合もあります。
また、「母親失格」・「あなたがいなければ」といったような、人権にかかわるような言動を繰り返す祖父母との同居では、状況がつらすぎます。
もちろん、きちんとした機関であればプライバシーも守られるので、安心して相談に行けますね。
「誰にも言えなくて一人でつらい」そんな場合には、早めに専門家の力を借りることを視野に入れるのも大切なことなのです。
6.「おかしい」と感じたら早めに受診を!早期発見・対処で重症化を防ぐ
うつをはじめ精神疾患は、インフルエンザのように急に高熱が出たり怪我のように出血が起こるわけではありません。
「病院に行くほどでもない」・「何かおかしいけれど気のせい」・「家を空けられない」このように思う、真面目な方ほど罹患しやすく重症化するまで手を打つのを我慢してしまいがちです。
精神の病院というと“精神科”、ということに抵抗がある方もおられるでしょう。しかし、「何かおかしい」を診てもらえる機関には、“心療内科”もあります。
心療内科では“内科”ともついているよう、心と体の両方の症状を診てもらえます。
先述のようにうつ等は高熱や出血は伴いませんが、以下のような体の異常がサインとなる場合も多いです。
- 頭痛
- 吐き気や胃腸不快症状
- 生理の乱れ等女性症状
- 不眠・過眠(眠れない・たくさん寝ても疲れが取れない)
- 注意力が低下している・やる気が起きない気がする
同居で疲れて、これらが気になる場合には、一度受診も視野に入れてみましょう。
何もなければ気持ちが楽になりますし、治療が必要であれば早めに受診をしたことで重症化を防げる場合もあります。
希望や必要に応じて、薬を使わない選択肢(鍼灸治療・カウンセリング等)を紹介してもらえる場合もあります。
長く密接な問題だからこそ、自分の心と向き合って!
同居問題の悩みを打ち明けたり調べてみると、「別居をすれば良い」・「二世帯住宅を建てれば良い」といったことを“解決策”と思っている方が多いように感じます。
同居問題は長く密接な問題です。子育てが絡むと、なおさらです。
だからこそ、ママは一人で悩んでしまいがちになったり、うつ等病気にもなりやすくなってしまうのでしょう。
子育てをしていると、つい自分のことは後回しになってしまいますし、子供と祖父母との関係のこともあり「“我慢”が最善策」と思ってしまうママも少なくありません。
しかし、今後も長く続く密接な問題だからこそ、ママはまずは自分を大切に考えることが重要です。
MARCH(マーチ)では、妊娠や子育ての先輩たちが、ためになる情報を毎日配信しています!新米ママ&パパはぜひご覧ください♪

まだデータがありません。